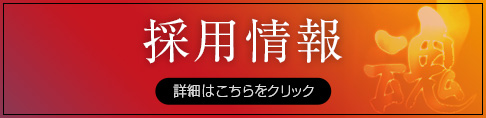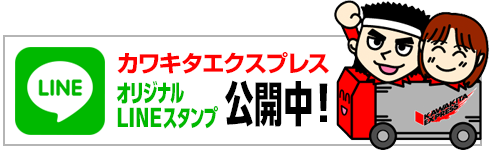企業の役割
かなり前だが、ファジーとか1/fゆらぎが流行った時期、日本人はあいまいだとか、白黒はっきりしないとか、結構批判気味に言われていた。
その時は「そうだ!そうだ!」と思ったが、最近はそれが日本人のいいところであり、人間として重要な感覚だと思うようになってきた。
当然、優柔不断だったり、心の中で思っていることをはっきり言わないというような面は、直すべきところだと思うが、なんでもかんでも「イエスかノーか」とはっきりすることがベストだとは限らない。
今までの仕事のやり方は、誰にでも分かるように、誰でも同じように出来るようにを基準に、マニュアル化したり、ルール化してきた。
その結果、指示があれば出来るが指示がないとできない応用の利かない人達を作ってきたような気がする。
うちでも一時期、ルール化・マニュアル化・制度化しようと躍起になっていた時期があった。
形を作れば簡単に人が育ち、一定の仕事が問題なくこなせると思っていた。
でも、感覚でやってきたことを形にするのは、事の他手間のかかる作業で思うように進まなかった。
そう考えていても実際に現場を回していかなければ、仕事は成り立たない。
結果的にはあまり形に表せないまま今日に至った。
ところが今はあまり説明をしなくても、自分と同じような方向性の発想をしてくれるスタッフが何人もいる。
何を心掛けてきたか?
それは「日常に起こる問題一つ一つを、都度都度の感覚で同じ方向に向かって解決してきた。」ということの積み重ねだと思う。
ルール化して、それに沿うようにするのは、出来上がった後は自動で物事が進む感じがする。
ある意味、楽かもしれない。
でもそれを求めていた時の自分の気持ちは「面倒くさいことから逃げていた」のだと今は思う。
ルール化せずに、起こった現象一個一個に対して処理していくのは、大変手間がかかる。
非効率かもしれない。
でも同じメンバーで同じ場所で同じ作業をしていても、昨日と今日は違うし、今日と明日は違う。
見た目は一緒でもそれぞれの「心の状態」が違う。
その同じでない状態をルール化はできない。
その場で感じるしかない。
感じながら結果はいつも同じ方向へ導いていかなければいけない。
その時に必要な感覚は、バランス感覚。
相手に合わしつつ自分を貫き、自分を貫きながらも相手に合わす。
注意をしながらほめて、ほめながら注意する。
責任を負わせつつも抜け道を作ってあげ、抜けすぎないように引き締める。
ちょっと小難しくいうと「中庸」という感覚が必要である。
バランスを取る時に重要なのは、「軸」である。
やじろべい・だるま・振り子などを、右に振ろうが左に振ろうが、前へ行こうが後ろに行こうが、いつも真ん中に戻ってくるのは、ぶれない「軸」があるからである。
人にとっての「軸」とは?
それは、夢だったり目標だったり、もっというと自分が存在する意味がちゃんと分かっている状態。
もっと簡単なことで言うと「思いやり」とか「人に迷惑をかけない」とか、人としての道理がわかっているということが、「軸」のある状態である。
あえて白黒はっきりさせなくても、あいまいな感覚で済んでいたのは、人間としてちゃんと「軸」を持っていたから。
それは人間として成熟していたということでもある。
成熟した者同士ならあえて説明をしなくても、当たり前のように分かち合えるものが、上っ面の現象のみで白黒をつけてきた結果、他人が作った尺度がなければ判断できないような薄っぺらい未熟な人間が増え、今のような社会になってしまった。
継承するという意味で、誰もがわかるように「見える化」を進めながら、最後は感覚で、何も見なくても同じ結果になるような「見えないものを感じる力」を持つ人に育てていくこと、それが企業としての社会的責任ではないかと思う。